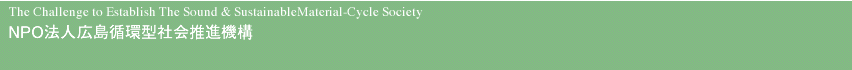令和7年度(2025)実施課題
実証1
【課題名】かき殻微粉砕品の規格化と工業応用
【代表者】 丸栄株式会社 ・ 沖野 靖将
【概要】県内で発生する牡蠣殻を県内で微粉砕し、県内等で自動車部品や建材など工業用途で活用される事を目標とする。
粉砕対象の原料をカキ殻内殻層に限定し、目標粒度を乾式粉砕に絞り規格化を進める。
量産化を視野に入れた粉砕評価試験を行い、プラスチック等生活用品コンセプトの試作と
それに用いる樹脂の評価を進め、食品接触用途の採用方法の試験ほか、粉体の規格では採用幅の広い用途対応を目指す。
粉体の粒度により流動性が異なるため、特に射出成形品での検証を進め、カキ殻の炭酸カルシウム鉱物としての特性を明らかにする。
また、牡蠣殻は海水中の溶存CO₂を固定して作られていることから、既存の鉱物製フィラー等と比較して利用によってCO₂固定できるという利点があり、製品粉末の負荷値をLCA等で数値化し、需要家の利用検討を促進する情報を取得する。
実証2
【課題名】草本系廃棄物を利活用した小規模バイオマス発電の発電手法に関する研究
【代表者】 三谷建設株式会社 ・ 福原 実苗
【概要】
*研究目的*
草本系廃棄物を利活用した小規模バイオマス発電手法の確立を目的とする。
*研究内容*
小規模バイオマス発電手法の確立を目標に,以下の3つの試験を計画する。
1)ペレット化試験:ペレットの発電用燃料としての価値を高めることを目的と
し,造粒条件や草本系廃棄物の混合比を複数設定してペレットの造粒を行う。
2)燃焼・発電試験:事業化に向けてペレット投入量・燃焼温度・送風量等を
変動因子とし,ペレット毎に燃焼・発電試験を行う。
3)成分分析:ペレットの成分は草・剪定枝の種類・配合比等により大きくば
らつくことが判明している。上記2)の結果も踏まえ,燃料としての性能面に
おける許容範囲の検討に資するデータ蓄積を目的とし,試験を実施する。
また,脱炭素・カーボンニュートラルにも配慮した,草本系ペレット製造プラントによる再資源化と小規模バイオマス発電のパッケージ事業を想定し,具体的な事業手法の検討及び事業採算性の試算を行う。
一般1
【課題名】食品製造業で発生する廃プラスチック類の熱回収システムの
開発
【代表者】デリカウイング株式会社 ・ 岡坂 和政
【概要】当社は大手コンビニエンスストア向けに弁当やおむすびなどを製造する食品メーカーです。
製造過程で年間を通して廃プラスチック類が発生しており、これが収集運搬業者や処分業者への負担となり、働き方改革の妨げになっています。
また、納入先からは2030年までに廃プラスチック類の排出量を2016年比で50%削減するよう求められています。現在は廃プラスチック類を破砕してセメント会社の燃料として利用しています。
【研究課題提案内容】
①令和6年度(2024年度)の調査では、「残渣付き廃プラ類」のリサイクル方法としてサーマルリカバリーが最適であり、燃料化にも問題がないことを確認しました。
令和7年度(2025年度)は、燃料化による熱回収方法の研究へ移行する予定です。また、連続供給での燃料化処理は困難で、小規模バッチ式熱回収システムの導入が必要です。
②令和7年度には、廃プラ類の各バッチ(回収袋)の成分にバラツキがあることを確認し、その原因が水分量や食品残渣の付着状況にあると判明しました。
各バッチの成分や発熱挙動を調査し、熱量の変動を評価する必要があります。さらに、熱回収効率を分析し、利用可能なエネルギー量を明確化する計画です。
【今後の計画】
2025年度:設備導入準備、2026年度:本格稼働、2027年度:効果確認、
2028~2029年度:水平展開、2030年度:目標達成
一般2
【課題名】動静脈連携に向けた資源循環システムの強化に関する研究
(自動車業界への再生プラスチックの利用拡大に向けて)
【代表者】 一般社団法人広島県資源循環協会 ・ 三谷 哲也
【概要】世界的にサーキュラーエコノミーへの移行が加速化している中,欧州においては,再生プラスチックの使用を義務付ける制度や規制案が発表されている。
昨年度の研究では自動車製造業における再生プラスチックの活用を対象とし,再生プラスチックの需要見込や県内での供給可能量を推計するとともに,動静脈連携の取組の促進に向けたボトルネックを整理した。
その結果,静脈側においては,「動脈側が要求する品質や量の再生プラスチックの供給」「動脈側の管理に必要となるデータ提供」が重要であることが明らかになった。
本研究においては,自動車業界への再生プラスチックの利用拡大をテーマとし,動静脈連携の構築に向けた研究を引き続き実施する。
特に,本年度の研究においては,動静脈連携に向けたボトルネックのひとつである「動脈側の管理に必要となるデータ提供」に着目し,動静脈連携に向けたデータ連携に関する仕組みづくりを目指す。
一般3
【課題名】特定層への市場調査を活用した発酵ヴィーガン栄養バーの品質向上
【代表者】 株式会社Rainbow Sake ・ 三宅 慶子
【概要】前事業年度に酒粕、柚子果皮、オリーブ粕の3種類の粕を使った、発酵ヴィーガン栄養バー(各種粕原料を粉砕またはペースト化し、混合成形し焼成した栄養補助食品)を開発した。
これら3種類の粕は、現状食品としての利用が少ない。広島県でのそれぞれの年間処分量は、酒粕約185トン、柚子皮約43トン、オリーブ粕約10トンと推測される。
前事業年度において、オリーブ粕の処理方法の開発と、1カ月の常温保存が可能となる為の条件をクリアしたレシピを開発した。
今年度は、当該栄養バーを、酒粕になじみのない人達への酒粕入門食としていきたい位置づけから、対象顧客を、酒粕に関して最もハードルの高い顧客層である、日本の若者や、海外の人達に絞り込み、これらの人達へのアピール力を高める要素を研究し、商品開発に役立てたい。
この為、まずは若者を対象とした専門家による市場調査を実施し、その結果から得られた情報を、栄養バーの品質向上に活用し、これらの人達への訴求力を高め、最終的に3種類の粕の処分量を減らしていきたい。
一般4
【課題名】流動化処理土の適用拡大のための強度・変形性能向上技術の
開発
【代表者】 丸伸企業株式会社 ・ 中野 貴文
【概要】建設汚泥あるいは残土のリサイクル材料である流動化処理土は品質が比較的不安定なため,建物地下空間の充填や地中埋設物周りの埋め戻しなど用途が限定される.
それに対し,構造性能(強度や変形性能)を向上させることができれば,支持地盤や杭引き抜き後の埋め戻し材としての利用など適用範囲が広がり,リサイクルの拡大につながることが期待される.
一方で,流動化処理土の品質は使用材料や外気条件にも左右されるが,広島地区では品質確保に適した土(シルトなど細粒分の多い土)の入手が難しくなくなりつつある.
そこで,これまで実施してきた構造性能確保のための各種リサイクル材料や混和剤の利用の有効性の確認をさらに進めて,さまざまな土材料や外気条件に対して安定した品質を得るための製造方法について,室内・現場実験により検討,確認し実用化をはかる.
一般5
【課題名】FRP/PE混合フレーク(FRP製LPG容器由来)の複合化押出加工による再資源化
【代表者】 中国工業株式会社 ・ 宇都宮 淳
【概要】本研究は、弊社が製造・販売しているFRP製LPG容器(以下、FRP容器)の低コストリサイクル方法の確立を目的とする。
過去に採択頂いた研究事業により、様々な材料で構成されたFRP容器を部材ごとに分離する技術は獲得できたが、FRPとPEが接着された状態の容器本体については、リサイクルにあたって多工程化によるコスト増がネックとなり、一定の成果は上がったものの、試作レベルでの技術獲得にとどまった。
本研究では、新しい「複合化押出加工」の技術を活用し、省コスト化を図ることによって、低コストのリサイクル方法確立を目指す。
一般6
【課題名】もみ殻利用の「籾プラ利用水稲育苗箱」の強度アップ製品
再試作開発品評価の反復実施
【代表者】 有限会社フラム ・ 小川 邦明
【概要】課題1:当社には、同業他社製品との強度比較検証データがない。
課題2:当社には、同業他社製品「水稲育苗箱強度」との同等強度に最適なもみ殻の「粉砕粉末の大きさ」及び「混合率」が、把握出来ていない。
課題3:当社のもみプラ水稲育苗箱には、吸湿による変形リスク・強度低下リスクがある。
概要1:広島県立西部工業技術センターに、同業他社製「水稲育苗箱」の強度を検証して頂き、現段階における当社もみプラ原料入り「水稲育苗箱」と強度等比較データを揃える。
概要2:自社の破砕及び混合ノウハウを生かし、もみ殻「粉砕粉末の大きさ」と「混合率」を探り当て、もみプラ製造原料を製造し、もみプラ育苗箱成形メーカーに、試作開発品の成型を外注する。
概要3:中山間地域米作り農家の視点に立ち、苗箱の一生視点からもみプラ水稲育苗箱の再試作品成型開発と第三者評価を粘り強く繰り返す。
一般7
【課題名】石州瓦のリサイクル技術の確立
【代表者】 桑本建材株式会社 ・ 霜江 健太
【概要】広島県の農村地帯や山間部、島嶼部へ行くと、かなりの人口減少が生じており、廃屋が増加しつつある。
そして、こうした廃屋を処分したり、改築したりするたびに、廃木材や廃土、廃コンクリートや廃瓦といった廃棄物が生じ、埋め立て処分場の面積が、減少してきている。
こうした点を鑑み、廃コンクリートや廃瓦の新たな用途を作り出すことで、
廃棄物を減らすようにしたいと考えている。
そのため、当社では、コンクリート廃材及び廃瓦の破砕装置を導入した。そして、コンクリート廃材の破砕は、事業化の軌道に乗せつつある。しかし、廃瓦の破砕物は、まだその応用分野を開拓できていない。
まずは、他社と似た応用分野を開拓するつもりであるが、それでも、基礎データを保有しておらず、競争力に乏しいと思われる。
そこで、この研究事業を使いながら、まずは、どういう応用分野がいいのか、根拠をはっきりとさせながら、需要の確立を目指したいと思っている。
一般8
【課題名】鋳造業で発生する産業廃棄物を有価物にするための研究
【代表者】 株式会社北川鉄工所 ・ 小川 莉奈
【概要】鋳物づくりには珪砂に粘土分を混ぜた砂の型を使用し、この砂は繰り返し使用後、産業廃棄物として捨てられます。
鋳物廃砂は、セメント原料や道路用骨材として再利用の実績がありますが、公共投資の状況に左右され、需要がなければ埋立処理となります。
鋳物づくりを行う上で多くの廃棄物を排出している現状を改善するため、鋳物廃砂が持つ金属分や炭素質、粘性、保水性を活かせる新たな用途を見つけ、効率よく活用する技術の確立を目指します。
本研究ではその第一段階として、活用にあたっての課題を把握し、解決するための調査及び市場ニーズの探索を行います。
一般9
【課題名】リチウムイオンバッテリーの非焙焼処理に関する研究
【代表者】 株式会社山陽レック ・ 廣瀬 敏典
【概要】近年あらゆる産業での電動化に伴いリチウムイオンバッテリーが普及しており、今後使用済みのリチウムイオンバッテリーが多量に発生することが予想されている。
このリチウムイオンバッテリーの処理では、加熱焙焼処理により無害化した後にバッテリー内部の有価性金属を回収によるリサイクル処理が一般的となっているが、処理に伴い発生する温室効果ガスの発生抑制も強く要望されてきている。
一方国外ではリチウムイオンバッテリーの非焙焼によるリサイクル処理を採用されていることから、今後非焙焼処理によるリチウムイオンバッテリーのリサイクルへの取組みも必要になってくると予想される。
本研究の最終目標をリチウムイオンバッテリーの非焙焼処理によるリサイクルを目的とし、非焙焼処理による処理技術や処理方法、及び課題等について検証するものとします。
一般10
【課題名】廃棄対象となるスサビノリの有効活用を目指した生物活性機能の探索とその応用に関する研究
【代表者】 福山大学 薬学部 ・ 杉原 成美
【概要】色落ちなどにより廃棄の対象となるスサビノリの有効利用を目的として、スサビノリの生物活性機能を探索する大学、スサビノリの養殖企業、地元特産品の開発を手掛けてきた企業が連携し、スサビノリ廃棄物に付加価値をつけることで有効利用につなげる研究を行う。
先ずは、有効利用につながるスサビノリの生物活性機能の探索を主として取り組む。
スサビノリの生物活性は、養殖場や収穫時期等によって異なる可能性が高いことから、養殖条件や形状の異なるスサビノリから抽出液を調製し、以下の3項目に関して研究を行う。
(1)形態の基本情報の収集と生物活性機能との関連における成分解析
(2)生物活性機能として抗菌作用の検討と応用に関する研究
(3)生物活性機能としてコレステロールの吸収抑制作用の検討と応用に関する研究
一般11
【課題名】酒粕甘酒の付加価値向上のための赤紫蘇飲料の開発
【代表者】 小野酒造株式会社 ・ 小野 晃
【概要】本事業でまずは酒粕甘酒の特性を理解していく。
酒粕は日本酒の製造方法によって品質が変わり、弊社(小野酒造株式会社)でも細かく分けると12種類の酒粕がある。
これらの酒粕の差異を確認するため、代表的な3種の酒粕を用いた甘酒をそれぞれ作製する。
麹甘酒との比較や乳酸発酵酒粕甘酒の特徴を調べるために成分分析を行う。一般成分分析や栄養成分をそれぞれ分析し、違いの確認や付加価値向上のための取組みに活用していく。
これらの分析と並行し、赤紫蘇エキスと酒粕甘酒をブレンドした試作品を作製する。日本酒特有の風味が苦手な人が多いため、赤紫蘇エキスや乳酸発酵の風味やマスキング効果によって改善を図っていく。
甘酒は、時間経過によって色の褐変が生じて見栄えが悪くなり、品質の劣化が起きてしまう。この経時変化について、各甘酒でどのような変化が生じるかも同様に分析する。
また商品開発に向けた酒粕の市場調査や発酵技術などの情報収集も随時行う。
一般12
【課題名】無電解ニッケルめっき廃液の減容化と微生物を利用したリン成分の再資源化
【代表者】 広島大学 大学院統合生命科学研究科 ・ 廣田 隆一
【概要】無電解ニッケルめっきは、化学処理によりニッケルを素材表面に析出させるめっき技術であり、自動車、機械・電子機器、半導体産業などにおいて欠かすことのできない表面処理技術である。
本技術は、溶液中のニッケルイオンを素材表面に沈着させ均一な被膜を形成するために、還元剤として次亜リン酸(H2PO2)を使用する。この反応で次亜リン酸は酸化されて不活性な亜リン酸(H3PO3)となり、めっき溶液は交換が必要な廃液となる。
廃液中に含まれるニッケルやリン(亜リン酸と次亜リン酸の混合物)は有価物であるが、分離が困難であるため、専門処理業者に引き取られた後、凝集沈殿されてスラッジとして回収、埋め立て処分されている。
本研究では、新規凝集剤・分離剤を用いたニッケルめっき廃液の減容化、および、リン成分の分離を試み、得られたリン成分について、微生物を用いた再利用プロセスの開発を試みる。
NPO独自課題
【課題名】がれき類等混合廃棄物の埋立量削減方策に関する研究
【代表者】 NPO法人広島循環型社会推進機構・研究・技術統括監 西村 和之
【概要】建設等現場から排出されるがれき類等混合廃棄物(以下、混合廃棄物)の埋立処分量(12万トン)は、最終処分量全体の三分の一を占め、埋立処分率は9%と広島県が廃棄物処理計画で目標とする1.5%を大きく超え、最終処分量削減のためには特に対策が必要な廃棄物種となっている。
コンクリート由来のがれき類はRC材としてリサイクルできるが、混合廃棄物にはRC材に適さない瓦、煉瓦、タイル等が入っており、RC材に適合するよう選別除去する必要がある。
また、選別後に埋立処分しないため、RC材以外の適切な用途(リサイクル手法を含めて)を見い出す必要がある。
そこで、混合廃棄物の埋立処分量削減の鍵となる選別手法及び選別後の用途を確立し、施策としての組み立てを図る目的で、混合廃棄物の排出状況や内容物の詳細に関する現状把握と喫緊にリサイクルすべき廃棄物の抽出とそのリサイクル手法を探索する。そのうえで、混合廃棄物の埋立量削減に対する効果的かつ効率的な道筋を提案する。